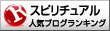第二巻 下つ巻 第二十六帖(六八)
⦿の国を真中(まなか)にして世界分けると申してあるが、⦿祀るのと同じやり方ぞ。天(あめ)のひつくの家とは天のひつくの臣民の家ぞ。天のひつくと申すのは天の益人(ますひと)のことぞ、江戸の富士と申すのは、ひつくの家の中に富士の形作りて、その上に宮作りてもよいのぞ、仮でよいのぞ。こんなにこと分けてはこの後は申さんぞ。小さいことは審神(さにわ)で家来の神々様から知らすのであるから、そのこと忘れるなよ。仏(ぶつ)も耶蘇(やそ)も、世界中まるめるのぞ。喧嘩(けんか)して大き声するところにはこの方鎮まらんぞ、このこと忘れるなよ。七月の三十一日、一二⦿。
第二巻 下つ巻 第二十七帖(六九)
この方は祓戸(はらえど)の⦿(かみ)とも現われるぞ。この方祀るのは富士に三(み)と所、@海(うずうみ)に三と所、江戸にも三と所ぞ、奥山、中山、一の宮ぞ。富士は、榛名(はるな)に祀りてくれて御苦労でありたが、これは中山ぞ、一の宮と奥の山にまた祀らねばならんぞ、@海の仕組も急ぐなれど、甲斐(かい)の仕組、早うさせるぞ。江戸にも三と所、天明の住んでいるところ奥山ぞ。あめのひつくの家、中山ぞ、富士が一の宮ざから気つけて置くぞ。
この方祀るのは、真中に神の石鎮め、そのあとにひもろぎ、前の右左にひもろぎ、それが「あ」と「や」と「わ」ぞ、そのあとに三つ、七五三とひもろぎ立てさすぞ。少しはなれて四隅(すみ)にイウエオの言霊石(ことたまいし)置いてくれよ。鳥居(とりい)も注連(しめ)もいらぬと申してあろがな、このことぞ。この方祀るのも、役員の仕事も、この世の組立(くみたて)も、みな七七七七と申して聞かしてあるのには気がまだつかんのか。
臣民の家に祀るのは神の石だけでよいぞ、天のひつくの家には、どこでも前に言うたようにして祀りてくれよ。江戸の奥山には八日、秋立つ日に祀りてくれよ、中山九日、一の宮には十日に祀りてくれよ。気つけてあるのに⦿の神示読まぬからわからんのぞ、このことよく読めばわかるぞ。今のようなことでは⦿の御用つとまらんぞ、正直だけでは⦿の御用つとまらんぞ。裏と表とあると申して気つけてあろがな、シッカリ神示(ふで)読んで、スキリと肝に入れてくれよ、読むたびごとに⦿が気つけるように声出して読めば、読むだけお蔭あるのぞ。七月の三十一日、一二⦿。
第三巻 富士の巻 第一帖(八一)
道はいくらもあるなれど、どの道通ってもよいと申すのは、悪のやり方ぞ、⦿の道は一つぞ、初めから⦿の世の道、変らぬ道があれば、よいと申しているが、どんなことしても我(われ)さえ立てばよいように申しているが、それが悪の深き腹の一厘ぞ。⦿の道は初めの道、⦿の成れる道、⦿の中の「 ・ 」なる初め、「 ・ 」は光の「 ・ 」、⦿は世の道、このこと気のつく臣民ないなれど。一が二わかる奥の道、身魂掃除すればこのことわかるのざ、身魂磨き第一ぞ。八月十日、⦿の一二⦿。
第三巻 富士の巻 第三帖(八三)
メリカもキリスは更なり、ドイツもイタリもオロシヤも外国はみな一つになりて⦿の国に攻め寄せて来るから、その覚悟で用意しておけよ。神界ではその戦の最中ぞ。学と神力との戦と申してあろがな、どこからどんなこと出来るか、臣民にはわかるまいがな、一寸先も見えぬほど曇りておりて、それで⦿の臣民と思うているのか、畜生にも劣りているぞ。まだまだ悪くなって来るから、まだまだ落ち沈まねば本当の改心出来ん臣民沢山あるぞ。
玉とは御魂(おんたま)ぞ、鏡とは内に動く御力ぞ、剣(つるぎ)とは外に動く御力ぞ、これを三種(みくさ)の神宝(かんだから)と申すぞ。今は玉がなくなっているのぞ、鏡と剣だけぞ、それで世が治まると思うているが、肝腎(かんじん)の真中ないのざ、それでちりちりばらばらぞ。アとヤとワの世の元要るぞと申してあろがな、この道理わからんか、剣と鏡だけでは戦勝てんぞ、それで早う身魂磨いてくれと申してあるのぞ。上下(うえした)ないぞ、上下に引っ繰り返すぞ、もう⦿待たれんところまで来ているぞ、身魂磨けたら、どんなところでどんなことしていても心配ないぞ、神界の都(みやこ)には悪が攻めて来ているのざぞ。八月の十二日、⦿のひつくの⦿。
第七巻 日の出の巻 第二十帖(二三三)
この度は世に落ちておいでなされた⦿⦿(かみがみ)様をあげねばならぬのであるぞ、臣民もその通りざぞ、⦿の申す通りにすれば何事も思う通りにスラスラと進むと申してあろがな。これからは⦿に逆らうものは一つも埓(らち)あかんぞ、やりてみよれ、九分九厘でグレンざぞ。⦿の国はどうしても助けなならんから、⦿が一日(ひとひ)一日と延ばしていることわからんか。皆の者が⦿を軽くしているからお蔭なくなっているのざぞ、世の元の神でも御魂(みたま)となっていたのでは真(まこと)の力出ないのざぞ。今度の経綸(しぐみ)は世の元の生き通しの⦿でないと間に合わんのざぞ。何処(どこ)の教会でも元はよいのであるが、取次役員がワヤにしているのぞ、今の様(さま)は何ごとぞ。
この方は力あり過ぎて失敗(しくじ)った⦿ざぞ、この世構う⦿でも我(が)出すと失敗るのざぞ、どんな力あったとて我出すまいぞ、この方がよい見せしめぞ。世界構うこの方さえ我で失敗ったのぞ、くどいようなれど我出すなよ、慢心と取違いが一等気障(きざわ)りざぞ。改心チグハグざから物事後先(あとさき)になりたぞ、経綸少しは変るぞ。今の役員、⦿の道広めると申して我(われ)を広めているでないか、そんなことでは役員とは言わさんぞ。今までは⦿が世に落ちて人が⦿になりておりたのぞ、これでは世は治まらんぞ。神が上(かみ)で、臣民、臣民で下におらねばならんぞ。吾(われ)が苦労して人救う心でないと、今度の岩戸開けんのざぞ、岩戸開きの御用する身魂は、吾の苦労で人助けねばならんのざ。
十年先は、五六七(みろく)の世ざぞ、今の人間、鬼より蛇より邪見ざぞ、蛇の方が早う改心するぞ、早う改心せねば泥海にせなならんから、⦿は日夜の苦労ぞ。道は一つと申してあろがな、二つ三つ四つあると思うてはならんぞ、足元から鳥立つと申してあろが、臣民火がついてもまだ気づかずにいるが、今に体に火ついてチリチリ舞いせなならんことになるから、⦿、くどう気つけておくのざぞ。三四気つけてくれよ、⦿の国は⦿の力で何事も思うように行くようになりているのに、学や智に邪魔されている臣民ばかり、早う気づかぬと今度という今度は取返しつかんぞ。見事なこと⦿がして見せるぞ、見事なことざぞ、人間には恐しいことざぞ、大掃除する時は棚のもの下に置くことあるのざぞ、下にあったとて見下げてはならんぞ。
この神は⦿の国の救われること一番願っているのざぞ、外国人も⦿の子ではあるが性来(しょうらい)が違うのざぞ、⦿の国の臣民が真(まこと)の⦿の子ざぞ、今は曇りているなれど、元の尊い種植えつけてあるのざぞ、曇り取り去りてくれよ、依怙(えこ)のようなれど外国は後まわしぞ、同じ⦿の子でありながら⦿の国の臣民の肩持つとは公平でないと申す者あるなれど、それは昔からの深い経綸であるから臣民にはわからんことであるぞ、一に一足す二でないと申してあろが、何事も⦿の国から⦿の民(たみ)からぞ、洗濯も同様ざぞ。今度の御用外(はず)したら、いつになりても取返しつかんことになるのざから、心して御用してくれよ、やり損ない出来ないことになりているのざぞ。天に一柱、地に一柱、火にも焼けず水にも溺(おぼ)れぬ元の種、隠しておいてのこの度の大立て替えぞ、どんなことあっても人間心で心配するでないぞ、細工は流々(りゅうりゅう)、仕上げ見てくれよ、この⦿はめったに間違いないぞ。三千年地に潜(もぐ)りての経綸で、悪の根まで調べてからの経綸であるから、人間どの心配せずに、⦿の申すよう素直に致して下されよ。
末法の世とは地の上に大将の器(うつわ)無くなりていることざぞ。オロシヤの悪と申すのは泥海の頃から生きている悪の親神であるぞ。北に気つけてくれよ、日本の国は結構な国で、世界の元の、真中の国であるから、悪神が日本を取りて末代の住居(すまい)とする計画で、トコトンの智恵出して、どんなことしてもするつもりで、いよいよを始めているのざから、よほど褌(ふんどし)締めて下されよ、日本の上に立ちている守護神にわかりかけたらバタバタに埓あくぞ。早う改心してくれよ。十二月二十六日、一二⦿。
第七巻 日の出の巻 第九帖(二二二)
人、⦿とまつわれば喜し喜しぞ、まつわれば人でなく⦿となるのぞ、それがマコトの神の世ぞ、⦿は人にまつわるのざぞ、「 ・ 」と〇と申してあろが、戦も「 ・ 」と〇と壊し合うのではないぞ、「 ・ 」と〇とまつろうことぞ、岩戸開く一つの鍵ざぞ、和すことぞ、⦿国真中(かみぐにまなか)に和すことぞ。それには〇(身)掃除せなならんぞ、それがこの度の戦ぞ、戦の大将が⦿祀らねばならんぞ。二四(西?)は剣(つるぎ)ざぞ。⦿まつりは神主ばかりするのではないぞ、剣と鏡とまつらなならんぞ、まつわれば魂(たま)となるのざぞ。魂なくなっていると申して知らせてあろがな、政治も教育も経済の大将も、⦿祀らねばならんのぞ。天(てん)の天照皇大神(あまてらすすめおおかみ)様はさらなり、天の大神様、地(くに)の天照(あまてらす)大神様、天照皇大神様、月の⦿様、とくに篤(あつ)く祀りくれよ、月の大神様 御出でまして闇の世は月の世となるのざぞ。素盞鳴の大神様も篤く祀りてくれよ、この⦿様には毎夜毎日(まいよまいにち)お詑びせなならんのざぞ、この世の罪穢(つみけがれ)負われて陰から守護されて御座(ござ)る尊い御(おん)神様ぞ、地(ち)の御神様ぞ、土(つち)の神様ぞ、祓い清めの御神様ぞ、国々の産土(うぶすな)の神様祀りくれよ、遅くなればなるほど苦しくなるのざぞ、人ばかりでないぞ。十二月八日、ひつ九のか三。
第八巻 磐戸の巻 第十六帖(二五二)
世の元からの生⦿(いきがみ)が揃(そろ)うて現われたら、皆腰抜かして、目パチクリさして、物言えんようになるのざぞ。神徳貰(もろ)うた臣民でないとなかなか越せん峠ざぞ、神徳はいくらでも背負いきれんまでにやるぞ、大き器(うつわ)持ちて御座れよ、掃除した大き要れ物いくらでも持って御座れよ、神界にはビクともしぬ仕組出来ているのざから、安心して御用勤めてくれよ。今度はマコトの⦿の力でないと何も出来はせんぞと申してあろが、⦿(ニホン)の国は小さいが、天と地との神力強い、⦿のマコトの元の国であるぞ。
洗濯と申すのは何事によらん、人間心捨ててしもうて、智恵や学に頼らずに、⦿の申すこと一つも疑わず、生れ赤子の心の初心(うぶこころ)になりて、⦿の教え守ることぞ。身魂磨きと申すのは、神から授かっている身魂の命令に従うて、肉体心捨ててしもうて、⦿の申すとおり背(そむ)かんようににすることぞ。学や智を力と頼むうちは身魂は磨けんのぞ。学越えた学、智越えた智は、⦿の学、⦿の智ざということわからんか。今度の岩戸開きは身魂から、根本から変えてゆくのざから、なかなかであるぞ、天災や戦ばかりでは中々埒あかんぞ、根本の改めざぞ。小さいこと思うているとわからんことになると申してあろがな、この道理よく肚に入れて下されよ、今度は上中下三段に分けてある身魂の因縁によって、それぞれに目鼻つけて、悪も改心さして、善も改心さしての岩戸開きざから、根本から造り変えるよりはどれだけ難しいか、大層な骨折りざぞよ。
叱るばかりでは改心出来んから、喜ばして改心さすことも守護神にありてはあるのざぞ、聞き分けよい守護神殿少ないぞ、聞き分けよい悪の神、早く改心するぞ、聞き分け悪き善の守護神あるぞ。この道の役員は昔からの因縁によって御魂(みたま)調べて、引寄せて、御用さしてあるのぞ、滅多に見当狂わんぞ、⦿が綱かけたら中々離さんぞ、逃げられるならば逃げてみよれ、くるくるわまってまた始めからお出直しで御用せなならんようになって来るぞ。身魂磨け出したら病神(やまいがみ)などドンドン逃げ出すぞ。出雲の神様大切申せと知らしてあること忘れるなよ。子(ね)の年真中にして前後十年が正念場、世の立て替えは水と火とざぞ。未(ひつじ)の三月三日、五月五日は結構な日ぞ。一月十四日、⦿の一二のか三。
第十巻 水の巻 第七帖 (二八一)
皆病気になりていることわからぬか。一二三祝詞(ひふみのりと)で治してやれよ。神示読みて治してやれよ。自分でもわからぬ病になっているぞ、早う治さぬとどうにもならんことになって来るぞ。この宮、仮であるぞ。真中に富士の山造り、そのまわりに七つの山造りてくれよ。拝殿(はいでん)造りくれよ。神示書かす所造りくれよ。天明休む所造りくれよ。いずれも仮でよいぞ。早ようなされよ。松の心にさえなりておれば、何事もすくすく行くぞ。五月四日、三のひつ九のか三。
第十三巻 雨の巻 第三帖(三三七)
草木は実(み)を動物虫けらに捧げるのが嬉しいのであるぞ。種は残して育ててやらねばならんのざぞ、草木の身が動物虫けらの御身となるのざぞ、出世するのざから嬉しいのざぞ、草木から動物虫けら生れると申してあろがな、人の身、神に捧げるのざぞ、神の御身(みみ)となること嬉しいであろがな、惟神の御身とはそのことぞ、神示よく読めばわかるのざぞ。この道は先に行く程広く豊かに光り輝き、嬉し嬉しの誠の惟神の道で御座(ござ)るぞ、神示よく読めよ、どんなことでも人に教えてやれる様に知らしてあるのざぞ。
いろはに戻すぞ、一二三(ひふみ)に返すぞ、一二三が元ぞ、天からミロク様は水の御守護遊ばすなり、日の大神様は火の御守護なさるなり、このこと魂までよくしみておらぬと御恩わからんのざぞ。悪も善に立ち返りて御用するのざぞ。善も悪もないのざぞと申してあろがな、⦿の国真中に神国になると申してあろがな、日本も外国も⦿の目からは無いのざと申してあろうが、⦿の国あるのみざぞ、わかりたか。改心すれば ・ の入れ替え致してその場からよき方に廻してやるぞ、何事も我がしているなら自由になるのであるぞ。我の自由にならんのは、させられているからざぞ、このくらいのことわからんで神国の臣民と申されんぞ、国々所々に宮柱太敷(みやばしらふとし)キ立てよ、たかしれよ。この先は神示に出したこと用いんと、我の考えでは何事も一切成就せんのざぞ、まだ我(が)出している臣民ばかりであるぞ。従うところには従わなならんぞ、従えばその日から楽になって来るのざぞ、高い所から水流れるようにと申して知らしてあろうがな。十月の十五日、ひつ九のか三。
第十二巻 夜明けの巻 第二帖(三二二)
⦿の国は⦿の肉体ぞと申してあるが、いざとなれば、お土も、草も、木も、何でも人民の食物となるように、出来ているのざぞ。何でも肉体となるのざぞ。なるようにせんからならんのざぞ。それで外国の悪神(あくがみ)が⦿の国が欲ししくてならんのざ。⦿の国より広い肥えた国いくらでもあるのに、⦿の国が欲しいは、誠の元の国、根の国、物のなる国、元のキの元の国、力の元の国、光の国、真中(まなか)の国であるからぞ。
何もかも、⦿の国に向って集まるようになっているのざぞ。神の昔の世は、そうなっていたのざぞ。磁石も⦿の国に向くようになるぞ。北よくなるぞ。⦿の国拝(おろが)むようになるのざぞ。どこからでも拝めるのざぞ。おのづから頭さがるのざぞ。
海の水がシメであるぞ。鳥居であるぞと申してあろうが、シメて⦿を押し込めていたのであるぞ。人民 知らず知らずに罪犯していたのざぞ。毎日、日日(ひにち)お詫せよと申してあろうが、シメて島国日本としていたのざぞ。
善き世となったら、身体(からだ)も大きくなるぞ。命も長くなるぞ。今しばらくざから、辛抱してくれよ。食べ物心配するでないぞ。油断するでないぞ。皆の者喜ばせよ。その喜びは、喜事(よろこびごと)となって天地のキとなって、そなたに万倍となって返って来るのざぞ。喜びいくらでも生まれるぞ。七月二十一日、アメのひつ九のか三。
第十四巻 風の巻 第一帖(三五二)
用意なされよ。いよいよざぞ、いよいよくるぞ。⦿(かみ)の御言(みこと)知らすぞ。知らすぞ。
眼覚めたら起き上がるのざぞ。起きたらその日の命頂いたのざぞ。感謝せよ、大親(おおおや)に感謝、親に感謝せよ、感謝すればその日の仕事与えられるぞ。仕事とは嘉事(よごと)であるぞ、持ち切れぬほどの仕事与えられるぞ。仕事は命ざぞ。仕事喜んで仕え奉(まつ)れ。我(が)出すと曇り出るぞ。曇ると仕事わからなくなるぞ。
腹減ったら食(お)せよ。二分は大親に、臣民腹八分でよいぞ。人民食べるだけは与えてあるぞ。貪(むさぶ)るから足らなくなるのざぞ。減らんのに食べるでないぞ。食(お)せよ。食せよ。一日一度からやり直せよ。ほんのしばらくでよいぞ。
⦿の道、無理ないと申してあろうが。水流れるように楽し楽しで暮せるのざぞ、どんな時、どんな所でも楽に暮せるのざぞ。穴埋めるでないぞ、穴要るのざぞ。苦しいという声この方(ほう)嫌いぞ。苦と楽、共に見てよ、苦の動くのが楽ざぞ。生れ赤児(あかご)見よ。子見よ、⦿は親であるから人民護(まも)っているのざぞ。大きなれば旅にも出すぞ、旅の苦楽しめよ、楽しいものざぞ。眠くなったら眠れよ、それが⦿の道ぞ。⦿のコト聞く道ざぞ。無理することは曲ることざぞ。無理と申して我が儘(まま)無理ではないぞ、逆(ぎゃく)行くこと無理と申すのざ。無理することは曲ることぞ、曲っては⦿の御言聞こえんぞ。素直になれ。火降るぞ。
相手七と出たら三と受けよ、四と出たら六とつぐなえよ、九と出たら一と受けよ、二と出たら八と足して、それぞれに十となるように和せよ。まつりの一つの道ざぞ。
〇-(おう)の世、⦿-(おう)の世にせなならんのざぞ、今は-〇の世ざぞ、-〇の世〇-の世となりて、〇-(おう)の世に ・ 入れて⦿-(おう)の世となるのざぞ。タマなくなっていると申してあろがな、タマの中に仮の奥山遷(うつ)せよ、急がいでもよいぞ、臣民の肉体、⦿の宮となる時ざぞ、当分宮なくてもよいぞ。やがては富士に木(こ)の花咲くのざぞ、見事富士にこの方鎮まって、世界治めるのざぞ、それまでは仮でよいぞ、臣民の肉体に一時は鎮まって、この世の経綸(しごと)仕組みて、天地(てんち)でんぐり返して光の世と致すのぢゃ。花咲く御代(みよ)近づいたぞ。用意なされよ、用意の時しばし与えるから、⦿の申すうち用意しておかんと、とんでもないことになるのざぞ。
〇-の世輝くと、☸となるのざぞ、☸と申して知らしてあろがな。役員それぞれの集団(まどい)作れよ、いずれも長(おさ)になる身魂(みたま)でないか。我(われ)軽しめる事は⦿軽くすることざ、わかりたか。おのもおのも頭領であるぞ、釈迦ざぞ。キリストざぞ。その上に⦿坐(ま)すのざぞ、その上 神また一束(ひとたば)にするのざぞ、その上にまた ・ でくくるぞ、その上にも ・ あるのざぞ、上も下も限りないのざぞ。
奥山何処(どこ)に変ってもよいぞ、当分肉体えおさまるから、何処へ行ってもこの方の国ぞ、肉体ぞ。心配せずにグングンとやれよ、動くところ、⦿力(ちから)加わるのざぞ、人民の集団(まどい)は⦿無き集団ぞ、⦿無き集団つくるでないぞ、⦿上に真中(まなか)に集まれよ。騒動待つ心悪と申してあること忘れるなよ、⦿の申したことちっとも間違いないこと、少しはわかりたであろうがな。
同じ名の⦿二柱(ふたはしら)あるのざぞ、善と悪ざぞ、この見分けなかなかざぞ、神示(ふで)読めば見分けられるように、よく細かに解いてあるのざぞ、善と悪、取り違いしていると、くどう気つけてあろうがな、岩戸開く一つの鍵ざぞ、名同じでも裏表ざぞ、裏、表と思うなよ、頭と尻 、違うのざぞ。千引(ちびき)の岩戸開けるぞ。十二月二十五日、ひつぐのか三。
第十五巻 岩の巻 第八帖(三七三)
この方のコト、肝(はら)にヒシヒシと響き出したら、善き守護神となったのざぞ。⦿の国の元のミタマと外国のミタマとスッカリ取り換えられているのにまだ目覚めんのか。⦿の国は真中(まなか)の国、土台の国、⦿の元の鎮まった国と申してあろうがな。十の国であるぞ、我(われ)さえよけら、よその国、よその人民どうなってもよいというほどに、世界の臣民、皆なりているが、表面(うわべ)ばかりよいことに見せているが、中は極悪ぢゃ。気づいている臣民もあるなれど、どうにも、手も足も出せんであろうがな。それが悪⦿に魅入(みい)られているのぢゃぞ。道はあるのに、闇、祓い清めて道見て進め。勇ましき弥栄の道、光りあるぞ。二月十六日、一二⦿。
第十九巻 まつりの巻 第十四帖(四一八)
旧九月八日から、祀り、礼拝、スックリ変えさすぞ、⦿代(かみよ)までにはまだまだ変るのぢゃぞ。祓いは祓い清めの⦿様にお願いして北、東、南、西、の順に柏手(かしわで)四つずつ打ちて祓い下されよ。⦿国の乱れ、声、キから。世界の戦(いくさ)、天災、皆人民の心からなり。人民一人に一柱(ひとはしら)ずつの守護神つけあるぞ、日本真中(まなか)、ボタン一つで世界動くぞ。八月十九日、一二⦿。
第十九巻 まつりの巻 第十六帖(四二〇)
日本の人民よくならねば、世界の人民よくならんぞ、日本の上の人よくならねば日本人よくならんぞ。祈る土地八つつくれよ。専一(せんいつ)、平和祈らなならんぞ、そのくらいわかっておろうが。今ぢゃ口ばかりぢゃ、口ばかり何もならんぞ、マコト祈らなならんぞ。真中の国、真中に、膝まずいて祈り事されよ。今度のお蔭(かげ)は神示よく読まねば見当とれんのざぞ。⦿はその人民の心通りに写るのであるから、因縁深い者でも御用出来んこともあるから、よほどしっかり致しておりて下されよ。八月二十日、一二⦿。
第二十一巻 空の巻 第二帖(四五七)
ひふみゆらゆらと一回二回三回唱えまつれよ、甦(よみがえ)るぞ。次に人は道真中にして〇(ワ)となり、皆の者集まりてお互に拝(おろが)み、 ・ (かみ)にまつりまつり結構ぞ、節分からでよいぞ。
このお道の導きの親尊べよ、どんなことあっても上(かみ)に立てねばならんぞ、順乱しては⦿(かみ)の働きないと申してあろうがな。(直会(なほらい)には神の座上につくらなならんのざぞ、神人共にと申してあろがな、)まだわからんのか、順正しく礼儀正しく、⦿にも人にも仕えまつれよ。束(たば)ねの⦿は、束ねの人は後(あと)からぢゃ、後から出るぞ。一月一日、一二⦿。
第二十二巻 青葉の巻 第十一帖(四八〇)
世界一(ひとめ)目に見えるとは、世界一度に見える心に鏡磨いて掃除せよということぢゃ、掃除結構ぞ。善と悪と取り違い申してあろうがな、悪も善もないと申してあろうがな、和すが善ざぞ、乱すが悪ざぞ、働くには乱すこともあるぞ、働かねば育てては行けんなり、気ゆるんだらすぐ後戻りとなるぞ、坂に車のたとえぞと申してあろうがな、苦しむ時は苦しめよ、苦の花咲くぞ。世は七度(ななたび)の大変り、変る代かけて変わらぬは、マコト一つの木(こ)の花ぞ、木の花咲くは二三(ふみ)の山、富士は⦿山、⦿住む所、やがて世界の真ん中ぞ。八月三日、ひつ九の⦿。
第二十七巻 春の巻 第三帖(六六〇)
掛巻(かけまく)も、畏(かしこ)き極(きわ)み、九二(くに)つ千(ち)の、清(すが)の中なる大清(おおきよ)み、清みし中の、清らなる、清き真中(まなか)の、よろこびの、其(その)真中なる、御光(みひかり)の、そが御力(みちから)ぞ、綾(あや)によし、十九立(トコタチ)まし、大九(オオク)二の十九立大神(トコタチオオカミ)、十四九百ヌ(トヨクモ)、十四(トヨ)の大神、瀬織津(せおりつ)の、ヒメの大神、速秋(ハヤアキ)の、秋津(アキツ)ヒメ神、伊吹戸(イブキド)の、主(ヌシ)の大神、速々(ハヤハヤ)の、佐須良(サスラ)ヒメ神、これやこの、太日月〇十(オオヒツキクニ)、皇神(スメカミ)の御前畏(みまえかし)こみ、謹(つつし)みて、うなね突貫(つらぬ)き、白(まお)さまく、ことの真言(マコト)を。伊行(いい)く水、流れ流れて、月速(つきはや)み、いつの程(ほど)にや、この年(とし)の、冬も呉竹(くれたけ)、一(ひ)と夜(よさ)の、梓(あずさ)の弓の、今とはや、明(あ)けなむ春の、立ちそめし、真玉新玉(またまあらたま)、よろこびの、神の稜威(みいづ)に、つらつらや、思い浮べば、天地(あめつち)の、始めの時に、大御祖神(オオミオヤ)、九二十九立(クニトコタチ)の、大神伊(オオカムイ)、三千年(みせとし)、またも三千年の、もまた三千年、浮きに瀬(せ)に、忍び堪(た)えまし、波風の、その荒々し、渡津海(ワタツミ)の、塩の八百路(やほじ)の、八汐路(やしほじ)の、汐(しお)の八穂合(やほあ)い、洗われし、孤島(こじま)の中の、籠(こも)らいし、籠り玉(たま)いて、畏(かしこ)くも、この世かまいし、大神の、時めぐり来て、一筋(ひとすじ)の、光の御代(みよ)と、出(い)でませし、めでたき日にぞ、今日の日は、御前畏こみ、御饌御酒(みけみき)を、ささげまつりて、海山野(うみやまぬ)、種々珍(くざぐさうづ)の、みつぎもの、供(そな)えまつりて、かごぢもの、ひざ折り伏(ふ)せて、大まつり、まつり仕(つか)えむ、まつらまく。生きとし生ける、まめひとの、ゆくりあらずも、犯(おか)しけむ、罪や穢(けが)れの、あらむをば、祓戸(はらへど)にます、祓戸の、大神達(おおかみたち)と相共(あいとも)に、ことはかりまし、神直日(かむなおひ)、大直日(おおなおひ)にぞ、見伊(みい)直し、聞き直しまし、祓(はら)いまし、清め玉いて、清々(すがすが)し、清(すが)の御民(みたみ)と、きこし召(め)し、相諾(あいうべな)いて、玉えかし、玉われかしと、多米津(ためつ、百取(ももとり)、さらに、百取の、机の代(しろ)に、足(た)らわして、横山(よこやま)の如(ごと)、波(なみ)の如、伊盛(いもり)、栄(さか)ゆる、大神の、神の御前(みまえ)に、まつらまく、こいのみまつる、畏(かし)こみて、まつらく白(まお)す、弥(いや)つぎつぎに。
新玉(あらたま)の玉の御年(みとし)の明け初(そ)めて罪(つみ)もけがれも今はあらじな。
節分の祝詞(のりと)であるぞ。太(ふと)祝詞せよ。いよいよの年立ち初(そ)めたぞ。嬉し嬉しの御代(みよ)来るぞ。(一月の三十日、日月神。)諾(うべな)う
ブログランキングに参加しています。記事を気に入ってくださいましたら、「ポチッ」とお願い致します。皆さまの応援が励みになります。